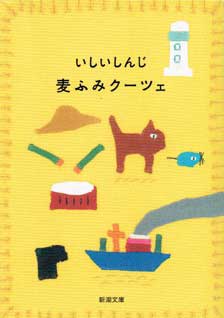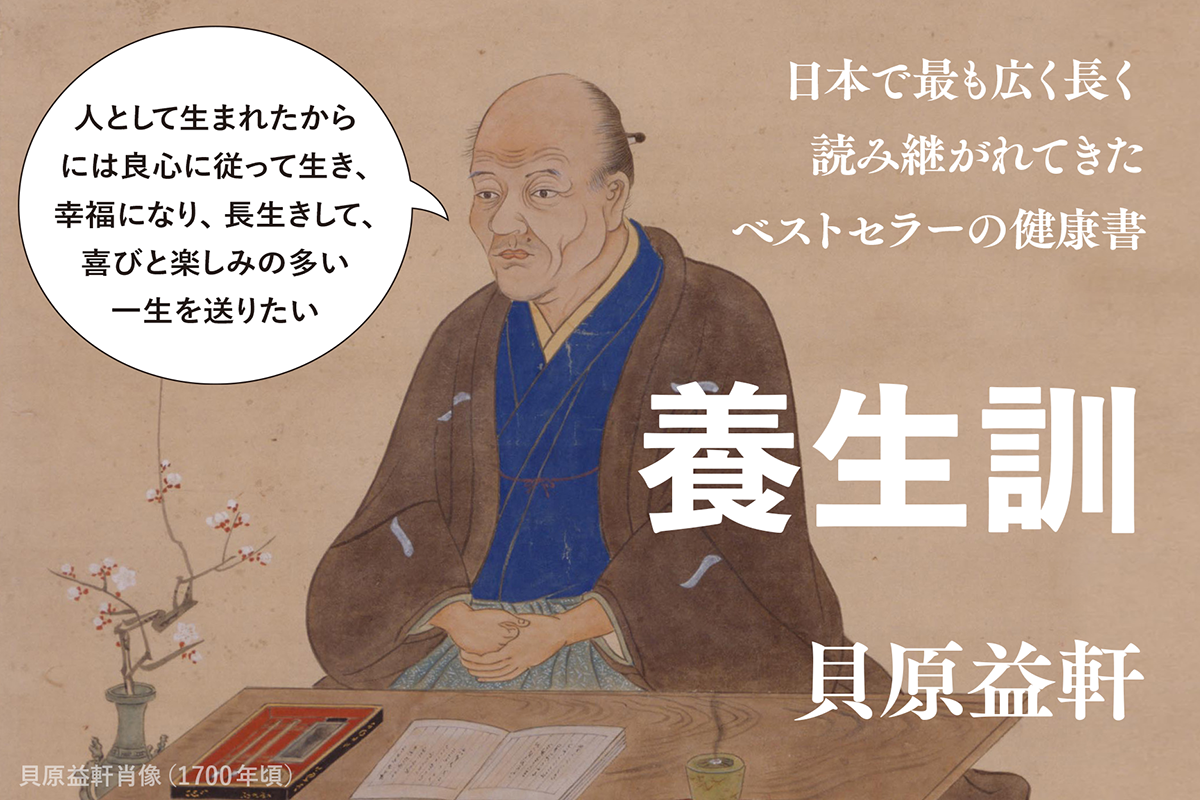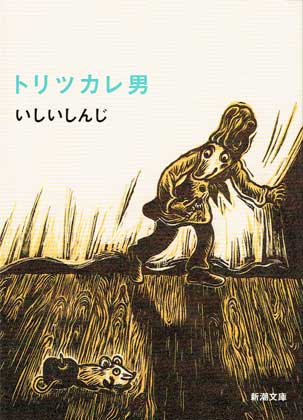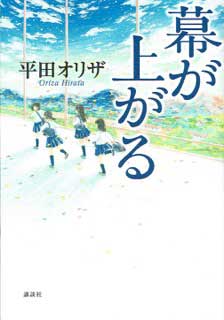生き活きナビ(サポート情報)腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ
透析の友・本の紹介【10】
井上靖 著『しろばんば』
2015.0.0
緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。
じんラボ をフォローして最新情報をチェック!
紹介する本:井上靖 著『しろばんば』
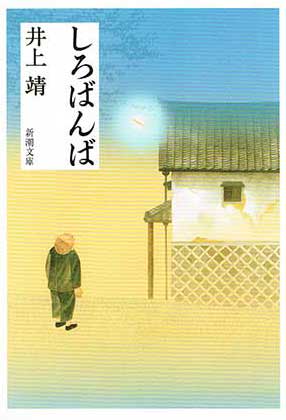 井上靖 著:新潮文庫(本体720円+税)
井上靖 著:新潮文庫(本体720円+税)
アマゾンで見る
この本のタイトルをご存知の方は私と同年配の方ではないかと思います。昔、小学校の国語の教科書で読んだ方も多いのではないでしょうか。歴史小説家である井上靖の自伝的三部作の第一部で、かなりの長編小説なのでじっくりと時間をかけて読むのにはちょうど良い本です。教科書に載るのはそのごく一部で、第一部前編の冒頭の“しろばんば”の説明と、第一部後編の四章、“どんどん焼き”の説明部分だったと思います。少し“しろばんば”の説明を引用してみましょう。教科書で読んだことがある方は、少し懐かしく思うかもしれません。
その頃、と言っても大正四、五年のことで、いまから四十数年前のことだが、夕方になると、決まって村の子供たちは口々に“しろばんば、しろばんば”と叫びながら、家の前の街道をあっちに走ったり、こっちに走ったりしながら、夕闇のたちこめ始めた空間を綿屑でも舞っているように浮遊している白い小さい生きものを追いかけて遊んだ。素手でそれを掴み取ろうとして飛び上がったり、ひばの小枝を折ったものを手にして、その葉にしろばんばを引っかけようとして、その小枝を空中に振り回したりした。(後略)
前編第一章より
私がこの小説を最初に読んだのは、静岡の三島市で暮らしていた大学1年の夏でした。主要な舞台は伊豆の山村である湯ヶ島で三島市からは目と鼻の先ということもあり、市内の書店に足を運ぶとこの本が平積みされていました。おそらく地元の子供たちの夏休みの課題図書になっていたのだと思います。私は自然の多い山間にある下宿で生活をしていたので、夕方ごろ草むらの中に羽虫がたくさん飛んでいるのを見て「あれが“しろばんば”なのか」と初めて気がつきました。
少し複雑な家庭環境の小学2年生の少年・洪作が主人公の物語です。父親は陸軍十五師団の軍人でその所在地である豊橋に住んでいます。母親と妹も父親と同じ豊橋にいるのですが、なぜか洪作一人が伊豆の湯ヶ島で暮らしています。教科書ではあまり詳しくは書かれていませんが、洪作は“おぬい婆さん”に育てられていて、このおぬい婆さんは曽祖父のお妾さんです。二人は祖父母や叔母が暮らす“上の家”(本家)とは離れた土蔵の中で生活をしています。冒頭では洪作の親族がたくさん出てきて少々面食らうかもしれませんが、読み進めると学期末の通知簿(成績表)をもらう日のエピソードや、夏休みに入って友達と渓谷の共同湯や池に飛び込んで遊ぶ情景などの描写に移ります。
初めて読んだときはあまり物語の中に印象を感じなかったのですが、今読み返してみると現代では見られない大正時代の田舎暮らしのことなどは興味深く感じました。この時代のライスカレーのことが書かれている箇所を読んで、カレーは古くから庶民の味だったのだなと気づきます。
通知簿を貰う日は、いつもおぬい婆さんは、彼女の最も自慢の料理であるライスカレーを作った。ライスカレーはいつもカレーの沢山はいったのと、カレーの少ししかはいらないのと二種類作った。洪作はおぬい婆さんとライスカレーを食べるのが好きだった。
「坊、食べてみな。辛い、辛いぞ。目から涙が飛び出すぞ」
おぬい婆さんは言った。洪作は薄い方のライスカレーだったが、それを食べる時はそうするものであるかのように、一口口に入れてみて、すぐ、
「おお、辛い! 」
と、顔をしかめてみせた。
(中略)
…おぬい婆さんの作ったライスカレーは美味かった。人参や大根や馬鈴薯を賽の目に刻んで、それにメリケン粉とカレー粉を混ぜて、牛缶の肉を少量入れて煮たものだが、独特の味があった。時々上の家でも作ったが、それとはまるで違っていた。
前編第二章より
 市販のカレールーを使わず、カレー粉でのライスカレーを再現してみました。
市販のカレールーを使わず、カレー粉でのライスカレーを再現してみました。
改めて読んでみて洪作と共に夏休みを体験しているような気持ちになりました。透析の時間を利用して少しずつ読み進んでいますが、やさしい文体には温もりが感じられ、不思議と穏やかな気持ちになっていきます。
物語の中盤で、洪作とおぬい婆さんは洪作の両親の住む豊橋に旅行します。今では湯ヶ島から愛知県の豊橋への移動はすぐですが、当時は今ほど交通機関が発展していません。バスの代わりに馬車を使い、小さな駅からは軽便鉄道での移動、沼津で一泊をしてから蒸気機関車に乗っての旅ですから、かなりの長旅です。初めて汽車に乗る緊張した洪作の姿が、次のようにユーモラスに描かれています。
やがて、きのう大仁から乗った軽便とは較べものにならない大きな怪物のような乗り物が、地響きをたててホームへ滑り込んで来た。おぬい婆さんは洪作の手を握り、決して離してはいけないと言った。荷物は夫婦者が窓から入れてくれることになったが、洪作は果たしてうまく荷物が入れられるかどうか不安な気持ちだった。それで洪作はおぬい婆さんに引き立てられながらも、荷物の方へ気を取られていて、汽車の上り口のところで足を滑らせて膝をついてしまった。汽車へ乗り込んでから、おぬい婆さんは洪作の足許を見詰め、
「洪ちゃ、下駄はどうした? 」
と言った。言われて初めて洪作は自分の足許に眼を落としてみたが、なるほど足は両方とも下駄を履いていなかった。
前編第四章より
大正時代の話ですから、もちろん私にとっては懐かしいと思えるものではありませんが、不思議と自分の小さかった頃のことが頭に浮かんできました。小学校に上がる直前に母の実家である長崎の佐世保へ寝台車に乗って行った時、年上の従姉妹が1ダースの鉛筆とクレヨン、スケッチブック、ノートなどをお土産に持たせてくれたことを詳細に思い出しました。お小遣いを捻出して、私のために文房具を揃えて待っていてくれた従姉妹の優しさに、40年が過ぎた今気がついたのです。この小説には、時代は違えど主人公が体験したことに近い体験を読者に思い出させてくれる力があるように思います。あなたがこの本を読んで思い出すのはどんな思い出でしょうか? ぜひ、読んでみてください。
この記事はどうでしたか?
生き活きナビ内検索
- 腎臓病全般
- ご家族の方